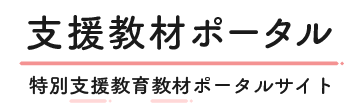実践事例
情報通信ネットワークとデータの活用に取り組むための指導
概要
・スマホのアプリは複数使えるが、PCの表計算ソフトウェアは使ったことがない生徒が多い。
・失敗を恐れ、検定試験への挑戦に対してやや消極的な姿勢が見られる。
・こだわりが強く、自分の好きな手順で作業を行おうとする生徒がいる。
・何に困っているのか捉えることができず、どのように支援を求めれば状況が改善できるか分からない生徒がいる。
・失敗を恐れ、検定試験への挑戦に対してやや消極的な姿勢が見られる。
・こだわりが強く、自分の好きな手順で作業を行おうとする生徒がいる。
・何に困っているのか捉えることができず、どのように支援を求めれば状況が改善できるか分からない生徒がいる。
不登校、コミュニケーション、学習支援
概要
・幼少期は誰とでも仲良くなる人なつっこい性格だった。しかし、小学校低学年から勉強が苦手になり、不登校になった。精神的に不安定になることもあり、高等部でも入学時より不登校の生活を続けているが、家庭では携帯電話を活用して友人と交流したり、調べものをしたりしている。タブレットに対する扱いも興味を持っている。
時間配分を考えながら物事に取り組むための指導
概要
・給食後に自分のおぼんを洗うことに取り組んでいるが、終了のタイミングがわからず、1枚のおぼんに対して10分以上洗い続けることがあった。また、普通のタイマーを使用して取り組んだが、あとどれくらい時間が残っているのかがわからず、時間内に表と裏が洗い終わらないことが多々あった。
物語『どうぞのいす』の内容を正しく読み取るための指導
概要
・病院のベッドサイドでの授業を毎日受けている。車いすに乗る機会が週3回あるが、病室から出ることはほとんどない。学校への登校は月に一度、1時間程度のみ。実際に見たり、聞いたりという経験が少ない。授業以外の時間はほとんどDVDを観て過ごしている。
・身体機能として、全身脱力状態で生活は全介助である。両手の親指と人差し指をわずかに動かすことができるが、具体物の操作は難しい。
・両手の親指のわずかな動きで紐を引く、スイッチの操作を取り入れた学習を行っている。
・身体機能として、全身脱力状態で生活は全介助である。両手の親指と人差し指をわずかに動かすことができるが、具体物の操作は難しい。
・両手の親指のわずかな動きで紐を引く、スイッチの操作を取り入れた学習を行っている。
ものを比べ、一番長いを判断するための指導
概要
・日常生活における簡単な指示を聞き取って行動することができる。
・1~10までの数で合成分解をすることができ、大小や多少も比較することができる。
・1~40までの数を10や5のまとまりで数えることができる。
・間違うことが苦手で、繰り返し間違えると目に涙をためる様子がある。
・長いという言葉の意味の理解と、具体物を比べて、長いを判断することが難しい。具体物(カラーテープ)の色のパターンで覚え、解答することがある。
・1~10までの数で合成分解をすることができ、大小や多少も比較することができる。
・1~40までの数を10や5のまとまりで数えることができる。
・間違うことが苦手で、繰り返し間違えると目に涙をためる様子がある。
・長いという言葉の意味の理解と、具体物を比べて、長いを判断することが難しい。具体物(カラーテープ)の色のパターンで覚え、解答することがある。
子どもの興味関心を引き出して、火災について知る指導
概要
・集中力が続かず、長時間の授業への参加は難しい。
・文字を書くことには苦手意識がある。
・授業参観などでは、周りの人が気になり、授業中でも歩き回ったり、話しかけたりする。
・集団での授業参加が難しい。
・文字を書くことには苦手意識がある。
・授業参観などでは、周りの人が気になり、授業中でも歩き回ったり、話しかけたりする。
・集団での授業参加が難しい。
ICT機器を使って、意思や思考を伝えながら教科学習をする指導
概要
・四肢及び体幹、首を動かすことは難しい
・瞼を完全に閉じることはできない
・瞳を上下左右に動かし、瞼を若干大きく開くことができる
・発声不可 若干唇が動く
・人工呼吸器装着
・瞼を完全に閉じることはできない
・瞳を上下左右に動かし、瞼を若干大きく開くことができる
・発声不可 若干唇が動く
・人工呼吸器装着
夏休みのタイムスケジュールを考えて、生活するための指導
概要
知的障がい
・一日のスケジュールを意識して過ごすことが難しく、長期休業中はゲームをしている時間が長い。
・自分の考えを書いたり、表出したりすることが苦手で時間がかかる。
・一日のスケジュールを意識して過ごすことが難しく、長期休業中はゲームをしている時間が長い。
・自分の考えを書いたり、表出したりすることが苦手で時間がかかる。
セルフレジを一人で利用するための指導
概要
・保護者と一緒に買い物に行くことが多く、買い物の大まかな手順を把握することができている。
・セルフレジを見たことはあるが、1人で使用する経験はまだない。
・繰り返し練習をすることで、自信を持って取り組めることが多い。
・セルフレジを見たことはあるが、1人で使用する経験はまだない。
・繰り返し練習をすることで、自信を持って取り組めることが多い。
自分が踊りたいダンスの動画を選び、みんなと一緒に踊るための指導
概要
・知的障がい。
・ダウン症候群のため、筋力が弱く、椅子の上に座る際、同じ姿勢を保つことができずに、姿勢を変えることが頻繁にある。
・一度に一つのことしか取り組むことが難しいため、学習や活動時に他のことを意識するように伝えると、現在している学習や活動場面に集中できなくなることが多くなる。
・ダウン症候群のため、筋力が弱く、椅子の上に座る際、同じ姿勢を保つことができずに、姿勢を変えることが頻繁にある。
・一度に一つのことしか取り組むことが難しいため、学習や活動時に他のことを意識するように伝えると、現在している学習や活動場面に集中できなくなることが多くなる。