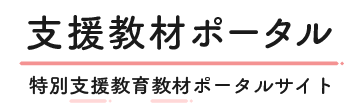実践事例
競技(ボッチャ)をするための指導、楽器の音を楽しむための指導
概要
・一日をベッド上で過ごす。
・自力で身体を動かすことは難しい。両目の眼球を上下左右に動かすことはできる。問いかけに対しては、眼球を上に動かして「はい」の返事をする。「いいえ」や「わからない」の返事は、眼球を動かすことはなく返事をしない。
・自力で身体を動かすことは難しい。両目の眼球を上下左右に動かすことはできる。問いかけに対しては、眼球を上に動かして「はい」の返事をする。「いいえ」や「わからない」の返事は、眼球を動かすことはなく返事をしない。
書くことへの負担を減らすための支援
概要
・読み間違いや飛ばし読みなど、文字を読むことに困難が見られる。
・文字を書くのに時間がかかり、集中力が落ちる。
・授業形態は基本的にプリント学習を採用している。
・手指の巧緻性に課題があり、iPadをタップする際に思っていた場所と違う場所が反応してしまう。
・文字を書くのに時間がかかり、集中力が落ちる。
・授業形態は基本的にプリント学習を採用している。
・手指の巧緻性に課題があり、iPadをタップする際に思っていた場所と違う場所が反応してしまう。
OneNoteを使った算数「合同と三角形」の学習
概要
・小学校に準ずる教育課程で、ほぼ学年に応じた内容を学習している。
・算数は学年相当で平均以上の力がある。
・5年生の児童は一人で、1対1で授業を行っている。
・右は人工内耳、左は補聴器を使用、装用値20dB。
・授業中はロジャーマイクを使用しているが、細部まで聞き取ることは困難。
・集中して学習できる。
・算数は学年相当で平均以上の力がある。
・5年生の児童は一人で、1対1で授業を行っている。
・右は人工内耳、左は補聴器を使用、装用値20dB。
・授業中はロジャーマイクを使用しているが、細部まで聞き取ることは困難。
・集中して学習できる。
指で操作することによって楽しみながら学習するための指導・支援
概要
・ノートに書くことに時間がかかる。
・書く量が増えるとやる気をなくす。
・仲間分けや線つなぎなど、紙のプリント上での操作が理解しにくい。
・ワークシートを前に生徒全体に説明をしていても、集中力を保てない生徒がいる。
・書く量が増えるとやる気をなくす。
・仲間分けや線つなぎなど、紙のプリント上での操作が理解しにくい。
・ワークシートを前に生徒全体に説明をしていても、集中力を保てない生徒がいる。
時間を意識し、見通しを持って次の活動に移るための指導
概要
ホワイトボードへ貼り付け型のスケジュールボードを提示しているが、その時に行っている活動(行動)の終了時間がわからず、見通しが持てない。
「自分で調べ学習をするための支援・指導」
概要
・大分県の観光地や名物、特産品などについて、自分の興味のあるものを調べてオリジナルの観光マップ・観光ブックを作成する学習活動で、各自でインターネットを活用して調べる際、検索ワードを入力するのが難しい生徒がいた。
・検索結果の中から、どのインターネットのサイトを開いて見ればよいのかを判断するのが難しい生徒がいた。
・インターネットのサイト内の膨大な文章の中から、必要な情報を読み取るのが難しい生徒がいた。
・検索結果の中から、どのインターネットのサイトを開いて見ればよいのかを判断するのが難しい生徒がいた。
・インターネットのサイト内の膨大な文章の中から、必要な情報を読み取るのが難しい生徒がいた。
修学旅行先でマップアプリを使って目的地まで行く指導
概要
・家庭でスマートフォンを扱うことがあり操作には慣れている。
・入力する施設名や、決まった文言であれば自分で検索することができる。
・初めて、行くところは不安があり、またどの方向に向かって歩いたらよいか分からない。
・入力する施設名や、決まった文言であれば自分で検索することができる。
・初めて、行くところは不安があり、またどの方向に向かって歩いたらよいか分からない。
一人一台のiPadを使った美術鑑賞を効率よく行うための指導
概要
・教科書や副教材に掲載されている絵画などを各自で鑑賞する際、具体的にどこを指しているのかわかりづらいことがある。
・鑑賞した感想を発表する、またプリントに感想を記入し提出する際、プリントなどを忘れたり無くしたりすることがある。また、発表の際に、具体的な箇所がわかりにいことがある。
・手話、指文字、筆談などによる指示で、的確な取組ができるが個人差がある。
・キーボードによる入力では、誤変換などで時間がかかり、効率が悪い場合がある。
・鑑賞した感想を発表する、またプリントに感想を記入し提出する際、プリントなどを忘れたり無くしたりすることがある。また、発表の際に、具体的な箇所がわかりにいことがある。
・手話、指文字、筆談などによる指示で、的確な取組ができるが個人差がある。
・キーボードによる入力では、誤変換などで時間がかかり、効率が悪い場合がある。
工程を忘れずに清掃するための指導
概要
・女子トイレの手洗い場を担当して清掃している。丁寧に清掃するためには注意すべき点が多く、やるべきことを忘れてしまい、丁寧で効率的な清掃ができていない。
・教師が見て言葉かけをしなければ、清掃の工程を飛ばしてしまう。
・教師が見て言葉かけをしなければ、清掃の工程を飛ばしてしまう。