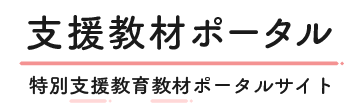実践事例
発表用ソフトウェアを活用した文の作成が苦手な生徒への指導
概要
コンピュータの導入により、ひらがなや漢字の読み書きでは、はねやとめ、はらい、全体の形のバランスなどに気をつけて、きれいな文字を書こうとする意識が少しずつ身に付いてきた。これまで、手指の運動機能や巧緻性の未熟さから、思うように書けなかったり、字を書くのに時間を要して意欲を失ったりしていたが、コンピュータの活用により生徒の文字学習への意欲が高まってきた。
ノートに文字や文章を書く時間と、コンピュータに入力する時間とを比べてみると、若干後者の方が早い。実際には少しの差であるが、生徒は、コンピュータ入力の方がかなり早いと感じている。それは、印刷によりすぐにきれいに仕上がる、間違えや脱字の修正がすぐにできる、非常に集中して取り組んでいることなどが要因として考えられる。また、コンピュータ入力に慣れることで、この差は広がることも予想される。教師のさりげない支援も回数を重ねるごとに減り、生徒によっては支援を全く必要としなくなると思われる。
これまで、国語の学習に自信がもてずに消極的だった生徒が、「またやりたい。」「コンピュータを使いたい。」などと申し出てくるようになった。また、ノートに書く学習にも一生懸命に取り組むなど、効果が目に見えて現れるようになってきた。
ノートに文字や文章を書く時間と、コンピュータに入力する時間とを比べてみると、若干後者の方が早い。実際には少しの差であるが、生徒は、コンピュータ入力の方がかなり早いと感じている。それは、印刷によりすぐにきれいに仕上がる、間違えや脱字の修正がすぐにできる、非常に集中して取り組んでいることなどが要因として考えられる。また、コンピュータ入力に慣れることで、この差は広がることも予想される。教師のさりげない支援も回数を重ねるごとに減り、生徒によっては支援を全く必要としなくなると思われる。
これまで、国語の学習に自信がもてずに消極的だった生徒が、「またやりたい。」「コンピュータを使いたい。」などと申し出てくるようになった。また、ノートに書く学習にも一生懸命に取り組むなど、効果が目に見えて現れるようになってきた。
プレゼンテーションフトウェアと電子黒板を活用した注意の持続が難しい児童への支援
概要
本児は、文房具がバラバラに置いてある教科書の図では、おしピンなどの特定のものを見つけることが難しい。大きく提示された画像が変化して、集中すべき箇所を示すことで、特定の文房具を見つけだすことができた。また、吹き出し(文字)による発問や指示は効果的であり、積木で遊ぶことがなかった。授業のまとめとして、バラバラに置かれた10個のブロックと、10のまとまりとして並べたブロックの画像をプロジェクタで同時に投影し、対比させることで、10のまとまりのよさに気づき、「10といくつ」の数え方を理解することができた。
ビデオ会議システムを活用した遠隔授業(ベッドサイド学習)
概要
病室のベッドの中での授業は、児童生徒にとって、時に孤立感を感じるものであるが、教室での授業にリアルタイム・双方向で参加できることで、病室に居ながら友達と一緒に授業を受けているという充足感が得られ、孤立感の軽減につながった。
コンピュータによる擬似体験を活用した知的障害のある生徒への情報モラルの指導
概要
本事例で、コンピュータを利用することにより、擬似サイトや事例、擬似体験から具体的な情報を得ることができた。また、犯罪に関わっている重大な問題であることも効果的に伝えることができた。
いくつかの事例を擬似体験しながら授業を進めていくうちに、生徒は互いの発言の中から、「出会い系サイト」の問題点や、自分たちが気を付けなければならないことなどに気付き始めていた。
いくつかの事例を擬似体験しながら授業を進めていくうちに、生徒は互いの発言の中から、「出会い系サイト」の問題点や、自分たちが気を付けなければならないことなどに気付き始めていた。
チャットを活用した聴覚障害のある生徒への情報モラル教育及びコミュニケーション手段の選択と活用
概要
○「手話」よりも複雑な表現が可能となり、特に専門分野の説明やカタカナ表記が容易に行える。
○「手話」は一連の動作であり、見落とす可能性もあるが、このシステムでは、スクリーン上に文字
を表示しておくことができる。
○生徒の文章表現が不適切であったり、日本語表記に誤りがあった場合、その場で指導できる
○「手話」は一連の動作であり、見落とす可能性もあるが、このシステムでは、スクリーン上に文字
を表示しておくことができる。
○生徒の文章表現が不適切であったり、日本語表記に誤りがあった場合、その場で指導できる
携帯電話の使い方を通してルールやマナーを考えさせる情報モラルの指導
概要
コンピュータ上でイラストや動画等を用いた擬似体験できる教材を
利用することで、現実感をもたせ、分かりやすく生徒に説明することができた。併せて、携帯電話会社が提供しているマナーやルール、仕組みについての教材を利用したが、ビデオ映像があると、生徒には理
解しやすいようであった。
利用することで、現実感をもたせ、分かりやすく生徒に説明することができた。併せて、携帯電話会社が提供しているマナーやルール、仕組みについての教材を利用したが、ビデオ映像があると、生徒には理
解しやすいようであった。
小学部11「タブレット端末を使い始めたばかりの児童が簡単にタブレット端末の操作になじめることをめざした事例」
概要
・小学部1年の集団での学習において、タブレット端末を使い始めたばかりの児童が簡単にタブレット端末の操作になじめることをめざした事例である。特別支援学校では同学年でも発達の段階や特性等が多様であり、集団の場面で同じアプリを使用して発表し合うことは難しいが、友達と見せ合うことができるようにカメラアプリで楽しく遊べるようにした。
小学部12「タブレット端末の基礎的な操作方法を習得しつつ、教科学習における目標達成のための活動を行った事例」
概要
・タブレット端末の基礎的な操作方法を習得しつつ、教科学習における目標達成のため、活用を図った。体験的に学習できるように、校舎内にある「〇」「△」「□」を探してタブレット端末で写真を撮る活動を行った。
撮った写真を児童が(マークアップで)編集し印刷した画像を形で弁別し、模造紙に貼る活動を通して、図形の仲間分けをすることができた。
撮った写真を児童が(マークアップで)編集し印刷した画像を形で弁別し、模造紙に貼る活動を通して、図形の仲間分けをすることができた。
小学部13「一人ひとりが活動内容を把握して主体的に取り組めることをめざし、タブレット端末を用いて、折り紙の折り方の動画を見ながら制作活動に取り組んだ」
概要
・自閉症のある児童が多いクラスでの自立活動の指導において、一人ひとりが活動内容を把握して主体的に取り組めることをめざし、タブレット端末を用いて、折り紙の折り方の動画を見ながら制作活動に取り組んだ。視覚優位の児童が多く、また、折る速さも一人ひとり違うため、個に応じたスピードで活動を進めることができた。
中学部1「発語のない生徒や、人前で明瞭に話すことが難しい生徒に対し、教材作成アプリ「Finger Board Pro」を使って、一人でスピーチができるような教材(教具)を作成した事例」
概要
・発語のない生徒や、人前で明瞭に話すことが難しい生徒に対し、教材作成アプリ「Finger Board Pro」を使って、一人でスピーチができるような教材(教具)を作成した事例である。行事の際にスピーチの代表を務め、タブレット端末を使って表現する力や、自己有用感が高まった。