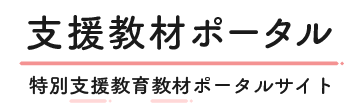実践事例
券売機を利用するための指導
概要
・経験が少なく、興味はあるものの実際に取り組んだことが少ない
・手順が複雑だと「できない」と言い、やる前から諦めてしまうことがある
・自分でやりたいという気持ちが強いため、教師からの直接的な支援が多すぎると機嫌を損ね、取り組みを中断することがある
・状況や場面が変わると、以前できていたことができなくなることがある
・手順が複雑だと「できない」と言い、やる前から諦めてしまうことがある
・自分でやりたいという気持ちが強いため、教師からの直接的な支援が多すぎると機嫌を損ね、取り組みを中断することがある
・状況や場面が変わると、以前できていたことができなくなることがある
興味・関心をもって主体的に音楽づくりに取り組むための指導
概要
・知的障がいと自閉スペクトラム症を併せ有している。
・「楽しそう」と感じたことに対しては、自分から積極的に取り組んだり、工夫して取り組んだりすることができるが、「難しい」と感じたことに対しては、積極的に取り組むことが難しく、取り組み方が雑になることが多い。
・ルールを理解していても、ルールを守ることが難しい場合がある。
・「楽しそう」と感じたことに対しては、自分から積極的に取り組んだり、工夫して取り組んだりすることができるが、「難しい」と感じたことに対しては、積極的に取り組むことが難しく、取り組み方が雑になることが多い。
・ルールを理解していても、ルールを守ることが難しい場合がある。
音楽を具体的なイメージを持って主体的に鑑賞しようとするための指導
概要
高等部1年は、職業生活科12名・生活教養科11名、合計23名で構成される。生活教養科においては、情緒に困りを持つ生徒が多く、学習段階としては、職業生活科と同等もしくはそれ以上という実態がある。音楽は、週1回の学年授業であり、生徒たちの興味関心を持つ視点や、取り組み方も様々である。
学習指導要領で示されているところの「鑑賞についての知識を得たり生かしたり」は、学年授業の共通課題として一緒に取り組むことができるが、提示した教材の「曲や演奏のよさなどについて(見いだし)自分なりに考え、曲全体を味わって聴くこと」の段階になると、個別の視点が必要となる。
学習指導要領で示されているところの「鑑賞についての知識を得たり生かしたり」は、学年授業の共通課題として一緒に取り組むことができるが、提示した教材の「曲や演奏のよさなどについて(見いだし)自分なりに考え、曲全体を味わって聴くこと」の段階になると、個別の視点が必要となる。
実習に見通しを持ったり、実習での経験を発表したりするための指導・支援
概要
・左半身の麻痺があるため一部介助が必要。
・言葉や文字だけではイメージが持ちにくい。
・簡単な日常会話を理解しているため、支援者の支持を聞いて行動することができるが、発語がないため自分の気持ちが相手に伝わりにくい。
・言葉や文字だけではイメージが持ちにくい。
・簡単な日常会話を理解しているため、支援者の支持を聞いて行動することができるが、発語がないため自分の気持ちが相手に伝わりにくい。
手順や留意点を確認しながらメンテナンス技能検定の練習に取り組むための指導
概要
・検定の操作を評価する際に友だちの操作を見逃してしまう。
・手順書の文章に集中してしまい、個別のアドバイスの内容をチェックし忘れてしまう。
・操作ができているのかできていないのか判断に迷い、次の操作を見逃してしまう。
・手順書の文章に集中してしまい、個別のアドバイスの内容をチェックし忘れてしまう。
・操作ができているのかできていないのか判断に迷い、次の操作を見逃してしまう。
場面緘黙がある生徒の「読み上げ機能」を使った意思伝達の支援
概要
・慣れない人や場では緊張が強く、緘黙になる。周りの人とは筆談やジェスチャーでやりとりを行う。
・これまでコミュニケーションツールとしてICT機器を活用した経験はない。
・「1年生を迎える会」での自己紹介の練習時に、読み上げ機能を紹介したが、考え込み返事がなかった。結局「生徒が文章を指差しながら、隣で教師が声に出して読む」ことを選択した。
・これまでコミュニケーションツールとしてICT機器を活用した経験はない。
・「1年生を迎える会」での自己紹介の練習時に、読み上げ機能を紹介したが、考え込み返事がなかった。結局「生徒が文章を指差しながら、隣で教師が声に出して読む」ことを選択した。
頭の後ろでバンダナを固結びする指導
概要
・視覚優位で言葉だけの説明ではイメージがしにくい。
・障がいの特性から忘れやすさがあり、既習事項を覚えていないことがある。
・左手に若干の麻痺があり、手指に強く力を入れたり、細かい手指の動きをしたりすることが難しい。
・障がいの特性から忘れやすさがあり、既習事項を覚えていないことがある。
・左手に若干の麻痺があり、手指に強く力を入れたり、細かい手指の動きをしたりすることが難しい。