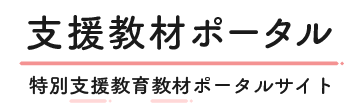実践事例
中学部12「他者からの問いかけ等に対して適切に応対することが難しい中学部生徒に対して、タブレット端末の無料通話アプリを活用して、電話の応対の仕方について学習した事例」
概要
・他者からの問いかけ等に対して適切に応対することが難しい中学部生徒に対して、タブレット端末の無料通話アプリを活用して、電話の応対の仕方について学習した。興味をもって取り組み、相手の話をよく聞いて、適切に応えようとする姿勢が見られるようになった。
中学部13「聴覚障害のある生徒タブレット端末を活用した指導に取り組んだ事例」
概要
・以下のようなタブレット端末を活用した指導に取り組んだ事例である。
1 「Google ドライブ」を活用した授業中の視覚支援と家庭学習支援
2 電子黒板、「ロイロノート・スクール」「EShare for SH」を組み合わせた効果的な指導方法
3「EShare for SH」、学習者用デジタル教科書、電子黒板を組み合わせた効果的な指導方法
4 タブレット端末等の ICT を活用し、「主体的に学習に取り組む態度」を育てる指導方法
1 「Google ドライブ」を活用した授業中の視覚支援と家庭学習支援
2 電子黒板、「ロイロノート・スクール」「EShare for SH」を組み合わせた効果的な指導方法
3「EShare for SH」、学習者用デジタル教科書、電子黒板を組み合わせた効果的な指導方法
4 タブレット端末等の ICT を活用し、「主体的に学習に取り組む態度」を育てる指導方法
中学部14「チャット機能を使って、クラス内で文字のやり取りを行い、タブレット端末に興味をもつことができるようになった事例」
概要
・本学級(中学部 1 年)の生徒は、家庭で保護者のスマートフォンを使って、動画を見たりゲームをしたりした経験はあるが、タブレット端末で文字入力をして、目的的な使用をした経験はほとんどなかった。そこで、タブレット端末の操作に慣れることを第一に考え、文字入力などの基本的な操作から始めることにした。文字入力の練習だけでは、生徒も興味を示さないので「Microsoft Teams」のチャット機能を使って、クラス内で文字のやり取りを行い、タブレット端末に興味をもつことができるようにした。
中学部15「生徒自身が課題を見つけ、自ら評価し、解決に向けて取り組むためのツールとしてタブレット端末等を利用し、課題解決に向けて主体的に取り組む姿勢が見られるようになった事例
概要
・持久走大会の練習において、生徒自身が課題を見つけ、自ら評価し、解決に向けて取り組むためのツールとしてタブレット端末等を利用した。タブレット端末の利用により自己評価や相互評価が容易になり、課題解決に向けて主体的に取り組む姿勢が見られるようになった事例である。
中学部16「質問にスムーズに答えることが難しく、コミュニケーションに消極的な中学部生徒に対して、タブレット端末を使ったリモート交流を行った事例」
概要
・質問にスムーズに答えることが難しく、コミュニケーションに消極的な中学部生徒に対して、タブレット端末を使ったリモート交流を行った事例である。教員や同級生等とのコミュニケーションの機会が増えることで、声の大きさを意識して自分なりに質問に答えようとするようになった。
高等部1「ICT 機器を使った情報活用能力の育成について研究を行った事例」
概要
・ICT 機器を使った情報活用能力の育成について研究を行った事例である。テーマを「コロナ禍でのコミュニケーションロスへの対応」、副題として「在宅であってもリアルと変わらないコミュニケーションをとる方法の提案」とし、「全国高校生プレゼン甲子園(※)」にチャレンジした。
(※)全国高校生プレゼン甲子園...全国高校生プレゼン甲子園実行委員会と一般社団法人プレゼンテーション協会の共催で行われているもので、論理的思考力、表現力、創造力等を養うとともに、互いの発表を通して、プレゼンテーションスキルの向上を図ることを目的としている。
(※)全国高校生プレゼン甲子園...全国高校生プレゼン甲子園実行委員会と一般社団法人プレゼンテーション協会の共催で行われているもので、論理的思考力、表現力、創造力等を養うとともに、互いの発表を通して、プレゼンテーションスキルの向上を図ることを目的としている。
高等部2「タブレット端末を活用し、本校の委員会活動を紹介するブログ制作を行った事例」
概要
・視聴覚委員会の活動として、タブレット端末を活用し、本校の委員会活動を紹介するブログ制作を行った事例である。視聴覚委員会は1~3年、総勢7名で構成され、活動頻度は月1回程度である。取材の後、「ドキュメント」を用い協働作業で原稿を制作した。端末で自分が作業しながら、他の生徒の進捗状況が分かる利点を生かし、学年の枠を超えて協力し、一つのものを作り上げることができた。
高等部3「「教科書の図版では確認できない細かな部分」をタブレット端末で確認することにより、視覚的に働きかけ、学習への興味・関心を高め、理解が深められるよう試みた事例」
概要
・本事例は、高等部(準ずる教育課程)の世界史 A における実践事例である。「教科書の図版では確認できない細かな部分」をタブレット端末で確認することにより、視覚的に働きかけ、学習への興味・関心を高め、理解が深められるよう試みた。また、教科横断的な視点に立った資質・能力の育成を図るべく、地理歴史科(世界史)と美術科の学習内容との関連付けも行った。タブレット端末で確認する絵画等については、信頼できる情報源(美術館の公式サイト)から情報を収集するよう指導した。
高等部4「生徒が一人で学んだことを実行でき、実践的な経験ができる事例」
概要
・以下のことが学べる事例である。
1生徒が一人で学んだことを実行でき、実践的な経験ができる。
2自らの努力や取組を他者から認めてもらい、他者の頑張りも知ることができる。
3コミュニケーションの仕方を実体験から学び、他者の取組からも学ぶことができる。
4いつでも振り返り、復習することができる。
1生徒が一人で学んだことを実行でき、実践的な経験ができる。
2自らの努力や取組を他者から認めてもらい、他者の頑張りも知ることができる。
3コミュニケーションの仕方を実体験から学び、他者の取組からも学ぶことができる。
4いつでも振り返り、復習することができる。
高等部5「プログラミング学習の導入に向けた初期学習として、使い慣れてきた「Keynote」のリンク機能を利用して2択クイズの演習を行った事例」
概要
・プログラミング学習の導入に向けた初期学習として、一般的な「Scratch」や「Springin’」等の専用アプリを使わず、使い慣れてきた「Keynote」のリンク機能を利用して2択クイズの演習を行った事例である。単純な仕組みを理解すれば、組み合わせを工夫することで、複雑で難易度や分野に幅のあるクイズにすることができる。選択肢や問題の数、問題の解説などを生徒自身で組み立てることができる。アニメーションを使えばゲームのようなエンターテイメント性をもたせることも可能である。
「Keynote」は単純な操作で、比較的完成度の高い制作ができるアプリである。ライブビデオ機能を使用して「YouTube」のようなゲーム実況中継風にプレゼンすることも可能である。
「Keynote」は単純な操作で、比較的完成度の高い制作ができるアプリである。ライブビデオ機能を使用して「YouTube」のようなゲーム実況中継風にプレゼンすることも可能である。