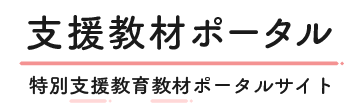実践事例
チャットを活用した視覚障害のある生徒と聴覚障害のある生徒のコミュニケーション
概要
視覚障害(弱視)のある生徒Aは、文字になった自分の発言を確認、修正しながら会話をすることができた。聴覚障害のある生徒Bは、言葉が文字で表現されることに安心し、笑顔で会話を楽しんでいた。
プレゼンテーションソフトウェアを活用した合奏の支援
概要
モニタ画面をタッチさせることで、ゲーム感覚で演奏の練習をすることができた。また、画面を見
て演奏することで、教師が指示をすることなく、児童自身が曲に合わせようと試み、伴奏パートはほ
ぼ正しく演奏することができた。ただ、すべての児童に有効とは言えず、特に身体模倣の苦手な児童
は興味を示さなかった。
て演奏することで、教師が指示をすることなく、児童自身が曲に合わせようと試み、伴奏パートはほ
ぼ正しく演奏することができた。ただ、すべての児童に有効とは言えず、特に身体模倣の苦手な児童
は興味を示さなかった。
電子黒板を活用した発達障害の児童への視覚的な支援
概要
視覚的に教材を提示できる電子黒板は、多くの児童にとって「分かりやすい」という評価を得ている(事前のアンケートより)。また、言葉だけの説明ではなかなか理解が難しい特別な支援を要する児童にも、図で見て考えることができるため、思考を促す重要な手助けとなっており、授業への意欲が高まった。
電子黒板は、障害のある児童の関心を引きつけ、一目で分かることに利点がある。また、注意の切り替えが苦手な場合、授業の進行に合わせて、手元の教材や教室の前方の教師、発表している他の児童の席などに注意を向けることが難しいが、電子黒板に提示された教材を画面上で変化させながら教師が説明したり、他の児童の発表の内容を提示させたりすることができるため、対象児童も集中して
取り組もうと努め、教師は授業の流れを中断することなく指導することができた
電子黒板は、障害のある児童の関心を引きつけ、一目で分かることに利点がある。また、注意の切り替えが苦手な場合、授業の進行に合わせて、手元の教材や教室の前方の教師、発表している他の児童の席などに注意を向けることが難しいが、電子黒板に提示された教材を画面上で変化させながら教師が説明したり、他の児童の発表の内容を提示させたりすることができるため、対象児童も集中して
取り組もうと努め、教師は授業の流れを中断することなく指導することができた
自作教材を活用した情報モラルの指導
概要
対象学級に在籍している発達障害の児童にとって、本教材のアニメーションは、単なる動く絵ではなく、セリフを吹き出しという形で表し、かつ音声も加えているため、視覚と聴覚の両方にはたらきかけ、物語の内容を理解しやすくなっている。ただ、1回視聴しただけでは難しかったので、ポイントとなるカットを静止画像で黒板に提示しながら、物語を振り返った。そうすることで、課題である内容について考える時間を十分に確保することができた。
デジタルカメラを活用した発達障害の児童への視覚的な支援
概要
本時の、「2つの写真を見てどうだった?」という発問に対しては、対象児童からも、「そろっていた方が、気持ちがいい。」「使いやすい。」といった意見が聞かれた。言語のみの説明や指導よりも、視覚的にとらえさせることで、理解しやすかったと思われる。生活習慣的な指導については、短時間でも継続して指導していくことが大切であり、今後も、靴箱のくつ、ロッカー等についても、時期を見て同様の指導を進めていきたい。
また、対象児童については、視覚的な支援の有効性が認められたので、写真と合わせて、絵カードやシンボルを活用したスケジュールボードや校内掲示の工夫等の支援を検討していく予定である。
また、対象児童については、視覚的な支援の有効性が認められたので、写真と合わせて、絵カードやシンボルを活用したスケジュールボードや校内掲示の工夫等の支援を検討していく予定である。
プレゼンテーションフトウェアを活用した 聴覚障害のある児童への視覚的な支援
概要
プレゼンテーションソフトウェアを使って写真資料を投し、「船の火事を消す」ことを写真で説明すると、「消す」という表現が、それまでの「消しゴムで字を消す」動作から「消防士が火事を消す」動作に変わった。それによって、消防艇の役目を読み取るとともに、「消す」という言葉の使い分けを理解することができたと考えられる。
黒板と話者(教師)が同時に児童の視界に入ることで、児童の視線移動が少なくなり、集中の持続につながるとともに、同じ画面に資料提示でき、時間短縮につながった。
黒板と話者(教師)が同時に児童の視界に入ることで、児童の視線移動が少なくなり、集中の持続につながるとともに、同じ画面に資料提示でき、時間短縮につながった。
コミュニケーションボードを活用した言語の表出が苦手な児童への支援
概要
コミュニケーションボードは紙媒体であるが、その使い方に慣れるために、さまざまな情報機器を補助的に活用した。会話の内容を広げ、学校生活で有効に活用できる語いの獲得・増加にもつながっている。授業では、文を作ると同時に自分の思いを表情や声に出して伝えようとする児童の姿がしばしば見られた。
また、興味のある絵記号とひらがなをつなげていくことで読字の力を伸ばしていくことができる。
また、興味のある絵記号とひらがなをつなげていくことで読字の力を伸ばしていくことができる。
プレゼンテーションソフトウェアを活用した読みの指導
概要
指マークにポインタを合わせ、色が変われば1回クリックするという約束を守り、自分のペースで話を進めることができた。また、「なぞなぞ」も挿入し、正解の場合、「おおあたり」をクリックすると、拍手の音が鳴るようにしたところ、意欲的に学習に取り組んだ。
ルールを守ったコンピュータ利用ができるようになると、日常生活においても順番や約束を守ることができるようになった。そのことが学校での集団活動においても、比較的落ち着いて過ごせることにつながったと考えられる。
ルールを守ったコンピュータ利用ができるようになると、日常生活においても順番や約束を守ることができるようになった。そのことが学校での集団活動においても、比較的落ち着いて過ごせることにつながったと考えられる。
VOCA等の情報機器を活用した生徒同士のコミュニケーション支援
概要
情報機器等の活用により、「教えて。」「もう一回。」といった生徒間の自然なやりとりの場面が見られるようになった。また、一人ひとりの活動が活発になると、全員が楽しみながら、明るい雰囲気の中で学習に取り組めるようになった。生徒の実態を把握し、柔軟な発想で様々な情報機器等を組み合わせることで、生徒の力が発揮された。
VOCA等の情報機器を活用した音声表出の難しい生徒の表現力を高める指導
概要
音声表出の難しい生徒は、教師の仲立ちがあって初めて生徒同士のかかわりの持てる場面が多い。だが、生徒は、友だちに自分の気に入った写真を分かってもらおうと写真の人物の服装や動作などについて、自分の知っていることばを組み合わせて表現方法を工夫した。教師を介さず、生徒同士で直接かかわることの楽しさを知った生徒たちは、授業時間だけでなく昼食時間、休み時間など生活全般で直接的なかかわり合いを楽しみ始めている。