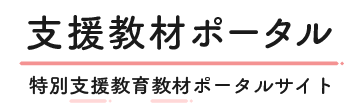実践事例
タブレットでプレゼンをする
概要
職場実習に向けて、内容を確認し他者に発表することで気持ちを高める。
職場実習をおえて学んだことや将来に向けた気持ちを振り返り、他者に伝える。
職場実習をおえて学んだことや将来に向けた気持ちを振り返り、他者に伝える。
事例