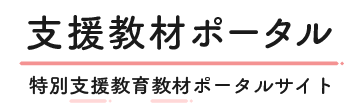実践事例
動作語の語彙を増やすための指導
概要
「写真」とアプリを利用して、動作を表したイラストの画像を一枚ずつ教師がiPadに表示させ,対象児が
「牛乳を飲む。」などとそのイラストにあった言葉で答えていく形式で学習を進めている。
「牛乳を飲む。」などとそのイラストにあった言葉で答えていく形式で学習を進めている。
事例
興味を持って活動に取り組むための指導
概要
各教科等を合わせた指導の時間にiPadの「効果音アプリ」を使用した。Bluetoothスピーカに接続して教室内で聞き
取れるようにした。
取れるようにした。
事例
ICT機器を使った国語科と算数科学習への取組
概要
意思伝達のコミュニケーション支援として、文字入力やシンボルを押すことで音声を発信したり、文字を書いたりすることで、相手への自分が伝えたいことを伝える。
事例
国語科授業のユニバーサルデザイン~考えが深まる授業を目指して~
概要
筆者が選んだ資料について考えることを通して、図や写真には筆者の意図があることを知り、一文にまとめることが出来る。
事例
文書読み上げソフトを利用した文章の聞き取り及び音読指導(個別指導)
概要
・聞くという手段で文章の内容理解を促す。
・読み上げの音声に続いて音読し、文章の読みの流暢性を向上させる。
・読み上げの音声に続いて音読し、文章の読みの流暢性を向上させる。
事例