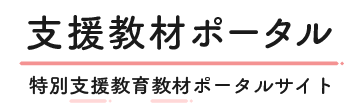実践事例
高等部6「書くことや表現することに苦手意識のある生徒に対して、「Google Classroom」を活用して、漢字などの知識を深めたり、意見を交換したりする学習を行った事例」
概要
書くことや表現することに苦手意識のある生徒に対して、「Google Classroom」を活用して、漢字などの知識を深めたり、意見を交換したりする学習を行った。「Google Forms」を使用したテストでは、生徒の知識・理解を効率的に確認できるようになった。「Google ドキュメント」をクラスで共有することで、生徒が文章で安心して表現できるようになった。また、それを大型提示装置に映すことによって
可視化が容易になった。
可視化が容易になった。
高等部7「弱視の生徒が学習する環境において、場面に応じた ICT 機器を活用してより効率的な学習を行うため、2種類のツールを実際に試した事例」
概要
・弱視の生徒が学習する環境において、場面に応じた ICT 機器を活用してより効率的な学習を行うため、タブレット端末と拡大読書器(移動テーブルの上に印刷物を置くとモニタに拡大されて映る仕組みで、白黒反転などが容易に行える機器)の2種類のツールを実際に試した事例である。「弱視の生徒に対し、どのような資料を提供していけばよいのか」に対するヒントを得ることができた。
高等部8「タブレット端末のアプリ「四字熟語クイズ-はんぷく一般常識」を利用し、四字熟語の学習を行った事例」
概要
・小学校中学年に配当されている段階の漢字をおおむね理解している高等部生徒に対し、タブレット端末のアプリ「四字熟語クイズ-はんぷく一般常識」を利用し、四字熟語の学習を行った事例である。
反復学習により、四字熟語の理解が高まり、日常的に四字熟語を利用するようになった。
反復学習により、四字熟語の理解が高まり、日常的に四字熟語を利用するようになった。
高等部9「数学科における体積の学習でタブレット端末の計測アプリを活用した事例」
概要
・数学科における体積の学習でタブレット端末の計測アプリを活用した事例である。タブレット端末に最初から入っているアプリ「計測」を使用するので、ポータル等からダウンロードする必要がない。
大きいものの長さを計測するときに、歩いたり、上を見上げたりするだけで数値が表示されるため、一人で測ることができる。さらには、巻き尺等の目盛りを読み取ることが苦手な生徒も測量することができる。
大きいものの長さを計測するときに、歩いたり、上を見上げたりするだけで数値が表示されるため、一人で測ることができる。さらには、巻き尺等の目盛りを読み取ることが苦手な生徒も測量することができる。
小学部1「音楽科の授業で、順番決めのアプリや簡単なピアノアプリを使い、活動への自主的な参加を促した事例」
概要
・タブレット端末にあまり触れたことがない児童に対し、音楽科の授業で、順番決めのアプリや簡単なピアノアプリを使い、活動への自主的な参加を促した事例である。
・ピアノ演奏を通して、音楽の楽しさに気付きつつ、自分でも演奏ができるという成功体験を積むことをめざした。活動に参加することが難しい児童が多かったが、タブレット端末の操作をきっかけに、タブレット端末を使用しない活動にも興味をもち、意欲的に参加する様子が見られるようになった。
・ピアノ演奏を通して、音楽の楽しさに気付きつつ、自分でも演奏ができるという成功体験を積むことをめざした。活動に参加することが難しい児童が多かったが、タブレット端末の操作をきっかけに、タブレット端末を使用しない活動にも興味をもち、意欲的に参加する様子が見られるようになった。
小学部2「活動の振り返り場面で、「Finger Board for students」で作成した自己評価シートを活用した事例」
概要
・活動の振り返り場面で、「Finger Board for students」で作成した自己評価シートを活用した事例である。自分の写真の横に、記号を使って自己評価をすることで、発語の有無に関わらず自己表現をしやすい環境を整えることができた。
小学部3「生活経験が乏しく、書字が困難である児童に対して、生活経験を増やしながら視知覚認知力、目と手の協応の能力を高めることで、読み書きの修得をめざした事例」
概要
・生活経験が乏しく、書字が困難である児童に対して、生活経験を増やしながら視知覚認知力、目と手の協応の能力を高めることで、読み書きの修得をめざした事例である。具体的には、ICT 機器を活用し視知覚認知能力を高めるトレーニングを行った。
小学部4「書くことに苦手意識のある児童に対し、タブレット端末の 50 音配列ソフトウェアキーボードとアプリ「えにっき」を活用して、日記を書く学習を行った事例」
概要
・書くことに苦手意識のある児童に対し、タブレット端末の 50 音配列ソフトウェアキーボードとアプリ「えにっき」を活用して、日記を書く学習を行った事例である。端末に入力することで、書くことへの負担感が軽減された。また、画像があることで、活動時の場面想起がしやすくなり、以前より意欲的に作文に取り組むようになった。読み上げ機能を使って、自分で文章を確認する姿も見られた。
小学部5「歩く活動への意欲を高めるためにタブレット端末を活用した事例」
概要
・右下肢に不自由のある小学部6年生で、散歩は好きだが外に出ると座り込んでしまうことが多い女子児童に対し、歩く活動への意欲を高めるためにタブレット端末を活用した事例である。タブレット端末を活用してからは、歩く姿をビデオで録画してほしいと要求することが多くなり、録画した動画を観ながら「よくがんばった」と振り返るようになった。動画で振り返ることが習慣になり、座り込むことなく歩き通すようになり、体力もついた。
小学部6「タブレット端末の操作の仕方を習得し、画面越しでの会話に慣れることを目標に学習を進めた事例」
概要
・家庭でのオンライン学習に備えて、タブレット端末の操作の仕方を習得し、画面越しでの会話に慣れることを目標に学習を進めた事例である。児童と教員が別室にいるので、事前の説明をよく聞くことや手順書を見ながら他者に頼らずにタブレット端末を操作することが必要となってくる。また、相手とのやり取りを円滑にするためには、画面への映り方や話し方の工夫が必要となってくるので、児童が自力で試行錯誤する様子が見られた。