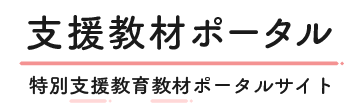実践事例
主体的に音楽づくりに取り組むための指導
概要
・知的障がい、てんかん
・初めて取り組むことや少し複雑な物事を理解することが難しく、「難しい」と感じたことに対しての抵抗感が強い。
・感情のコントロールが難しく、自分の要求が通らないと気持ちが不安定になり、大きな声が出ることが多い。
・初めて取り組むことや少し複雑な物事を理解することが難しく、「難しい」と感じたことに対しての抵抗感が強い。
・感情のコントロールが難しく、自分の要求が通らないと気持ちが不安定になり、大きな声が出ることが多い。
作曲することで、音楽の仕組みや要素を楽しみながら主体的に理解しようとするための指導
概要
高等部1年は、職業生活科12名・生活教養科11名、合計23名で構成される。生活教養科においては、情緒に困りを持つ生徒が多く、学習段階としては、職業生活科と同等もしくはそれ以上という実態がある。音楽は、週1回の学年授業であり、様々な実態の生徒たちが、興味・関心を持つ視点や取り組み方も様々である。
「音楽を形づくっている要素とその働き」について、学習指導要領では、表現(歌唱・器楽・身体表現)や鑑賞の活動において併せて学ぶようにとされているが、実際の授業では、表現では、取扱曲の個々に必要な部分のみの理解に留まることが多く、鑑賞では、曲の特徴や感受したことをどう表現していいのか迷う場面が多い。
「音楽を形づくっている要素とその働き」について、学習指導要領では、表現(歌唱・器楽・身体表現)や鑑賞の活動において併せて学ぶようにとされているが、実際の授業では、表現では、取扱曲の個々に必要な部分のみの理解に留まることが多く、鑑賞では、曲の特徴や感受したことをどう表現していいのか迷う場面が多い。
言葉で発表をすることを目指して、会の司会をひとりで取り組むための指導
概要
・場面緘黙で、家族や小さい頃から関わりのある人としか会話をしない。
・どうしていいのか分からないと動きが止まってしまう。
・どうしていいのか分からないと動きが止まってしまう。
フェルトボールの数を見て、何個と何個で5になるか合成・分解の表し方で答える学習
概要
・手元の操作や視覚情報が多いと、集中が続かなくなるこ
とがある。
・集中が続かなくなるため、学習に消極的になったり、離席したりすることがある。
とがある。
・集中が続かなくなるため、学習に消極的になったり、離席したりすることがある。
身近なものの形を見つけるための指導・支援
概要
・丸、三角、四角の形の学習で形の図形カードの弁別はできるが、身近なものの形を捉えることが難しい。
・教師が指差しをすると視線を向けるが、見続けることは難しい。また、指差しているところが分からないことがある。
・教師が指差しをすると視線を向けるが、見続けることは難しい。また、指差しているところが分からないことがある。
主体的に見通しをもって学習に取り組むための支援
概要
・手指を使った課題は得意だが、プリント学習で文字の読み書き、計算することに苦手意識が見られる
・自分の得意な課題には熱中して取り組むが、苦手な課題には「したくない」と拒否感を示す
・次の活動の時間になっても、得意な課題を続けようとする
・次の活動への見通しをもつことが難しい
・集中力が持続しにくい
・自分の得意な課題には熱中して取り組むが、苦手な課題には「したくない」と拒否感を示す
・次の活動の時間になっても、得意な課題を続けようとする
・次の活動への見通しをもつことが難しい
・集中力が持続しにくい
不登校生徒への遠隔面談や学習指導
概要
・入学時より不登校の生活を続けているが、家庭では携帯電話を活用して友人と交流したり、調べものをしたりしている。タブレットにも興味を持っている。国語の漢字の学習をもっと行いたいという意欲もあるので現在はプリント学習を続けている。電話での会話は「はい」や「いいえ」などの言葉が多いため、もう少し会話の機会を持ちたいと思っている。友人とはLINEで長い文章のやりとりができるので、タブレットを利用してコミュニケーションの機会を増やすことが登校への刺激になる可能性があると考えた。
集団活動に入ることに困難がある生徒の授業参加のための指導
概要
・簡単な質問であれば、口頭で答えることができる
・文字を書くときは、視覚的に確認できるものがあると書くことができる
・見通しが立たないと、落ち着かなくなる
・他の児童生徒の姿が視界に入ると気持ちが不安定になる
・文字を書くときは、視覚的に確認できるものがあると書くことができる
・見通しが立たないと、落ち着かなくなる
・他の児童生徒の姿が視界に入ると気持ちが不安定になる
えにっきアプリを使って発表しよう
概要
対象児童は1年生の頃からほぼ登校できていない状況で、学習経験が少ない傾向にある。口頭でのコミュニケーションには困りが見られる傾向があり、場面緘黙のある児童である。学校生活の中で話しをすることはないが、質問して耳を寄せると小さな声で話をしてくれる。そして、発表の場などで、人前に立つことや、「教えてくれる人?」と尋ねたりする時に進んで手をあげることができたりする積極性もある。書くことはあまりスムーズにはできないが、ローマ字の習得ができており、タイピングで打つ能力は高い。
活動移行時に不安定にならないための支援
概要
・活動に区切りをつけて切り替えることが難しい。
・好みの学習や活動が終わると不安定な状態になる。
・視覚的な支援や教師の誘導があれば正しく行動できることが多い。
・教室の時計やホワイトボードに記したスケジュール表では、活動の終了時刻が意識しにくい。
・好みの学習や活動が終わると不安定な状態になる。
・視覚的な支援や教師の誘導があれば正しく行動できることが多い。
・教室の時計やホワイトボードに記したスケジュール表では、活動の終了時刻が意識しにくい。