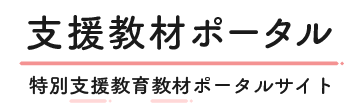実践事例
中学部2「ボディイメージを意識できるようにするため、身体の部分(目・鼻・口・肩・膝・肘・かかと)をタブレット端末と大型ディスプレイを組み合わせて視覚的に提示しながらストレッチを行った事例」
概要
・授業初めに、ボディイメージを意識できるようにするため、身体の部分(目・鼻・口・肩・膝・肘・かかと)をタブレット端末と大型ディスプレイを組み合わせて視覚的に提示しながらストレッチを行った事例である。
・授業中には、サーキットで行う活動(姿勢保持・バランスボール・平均台・ジャンプ・ミニハードル等)の様子を記録し、授業終盤の振り返りの時間で生徒一人ひとりの活動を写真や動画で見て、できたところや頑張っていたところなどを確認し、意欲を高めた。
・授業中には、サーキットで行う活動(姿勢保持・バランスボール・平均台・ジャンプ・ミニハードル等)の様子を記録し、授業終盤の振り返りの時間で生徒一人ひとりの活動を写真や動画で見て、できたところや頑張っていたところなどを確認し、意欲を高めた。
中学部3「スタイラスペンを使うことで、失敗を恐れずに何度も描きなおしたり色を塗り替えたりして、積極的に活動することをめざした事例」
概要
・鉛筆で描くときに力が入りすぎて線がうまく引けない生徒に対し、スタイラスペンを使うことで、失敗を恐れずに何度も描きなおしたり色を塗り替えたりして、積極的に活動することをめざした事例である。iPad のアプリを使った初めての作品作りであったが、事前に絵コンテで計画することで、12コマのパラパラ漫画式の動画をタブレット端末のアプリを使って作成することができた。
中学部4「主体的に学ぶことや学ぶことの楽しさ、自分の世界が広がっていく喜びを味わうことができるように、新たな学びの場を提供した事例」
概要
・多様な教育的ニーズに対応し、主体的に学ぶことや学ぶことの楽しさ、自分の世界が広がっていく喜びを味わうことができるように、タブレット端末や自分で操作できるデジタル機器を使用したり、遠隔によるオンライン授業を積極的に取り入れたりして、新たな学びの場を提供した事例である。
中学部5「体育の授業で、「Google Classroom」を活用し、学習内容を事前に提示したり、道具の設置場所の図を示したりした事例」
概要
・体育の授業で、「Google Classroom」を活用し、学習内容を事前に提示したり、道具の設置場所の図を示したりした事例である。
・コロナ禍により体育館での授業も生徒同士の距離の確保が必要となる中、各生徒が 1 台ずつタブレット端末を持っていることで説明をわかりやすく伝えることができた。また、事前に学習内容を示しておくことで授業中での説明が最小限となり、体を動かす時間を確保できた。バスケットボールのチェストパスや、マット運動の前転や後転など、手本の動画を入れておくことで、体育の授業時間以外でも質問が増え、学習意欲が高まった。
・コロナ禍により体育館での授業も生徒同士の距離の確保が必要となる中、各生徒が 1 台ずつタブレット端末を持っていることで説明をわかりやすく伝えることができた。また、事前に学習内容を示しておくことで授業中での説明が最小限となり、体を動かす時間を確保できた。バスケットボールのチェストパスや、マット運動の前転や後転など、手本の動画を入れておくことで、体育の授業時間以外でも質問が増え、学習意欲が高まった。
中学部6「文章を書くことが苦手な生徒に対し、タブレット端末のカメラ、予測変換機能、アプリを活用して暑中見舞いや年賀状を書く学習を行った事例」
概要
・文章を書くことが苦手な生徒に対し、タブレット端末のカメラ、予測変換機能、アプリを活用して暑中見舞いや年賀状を書く学習を行った事例である。文字を書くことへの負担が軽減され、絵文字スタンプや写真を自由に使うことで、積極的、主体的に取り組むことができた。
中学部7「人前で自分の考えを発表する機会が少ない生徒が、自分が選んだ本についてプレゼンテーションを行い、参加者による投票で「チャンプ本」を選ぶ、知的書評合戦「ビブリオバトル」に取り組んだ事例」
概要
・人前で自分の考えを発表する機会が少ない生徒が、自分が選んだ本についてプレゼンテーションを行い、参加者による投票で「チャンプ本」を選ぶ、知的書評合戦「ビブリオバトル」に取り組んだ。
読書が苦手な生徒も本を選ぶことから始め、本の面白さを相手に分かりやすく伝えるためにタブレット端末を活用し、工夫を凝らしたプレゼンテーションを行った。投票後は、発表者の良かったところや改善点についての評価を基に振り返りを行い、次の活動に向けて意欲を高めた。
読書が苦手な生徒も本を選ぶことから始め、本の面白さを相手に分かりやすく伝えるためにタブレット端末を活用し、工夫を凝らしたプレゼンテーションを行った。投票後は、発表者の良かったところや改善点についての評価を基に振り返りを行い、次の活動に向けて意欲を高めた。
中学部8「誤字の修正や新出漢字の書き方の指導を、口頭で受けることに強い抵抗を示す生徒に対し、連絡帳の日課の記入で使う漢字の習得をめざして、タブレット端末のアプリを活用した事例」
概要
・誤字の修正や新出漢字の書き方の指導を、口頭で受けることに強い抵抗を示す生徒に対し、連絡帳の日課の記入で使う漢字の習得をめざして、タブレット端末のアプリを活用した事例である。アプリを介した指導には抵抗がなく、徐々に端末の操作にも慣れ、現在は主体的に取り組むようになった。その他の活動でも、タブレット端末を活用して、できるだけ漢字で書こうとする意識が高まった。
中学部9「技術科で制作した作品を互いに見ながら、文書ソフトの共同編集機能を活用し、意見交換を行った事例」
概要
・中学部3年生の5名を対象に、技術科で制作した作品を互いに見ながら、文書ソフトの共同編集機能を活用し、意見交換を行った事例である。意見を考えたり、記入したりすることに対する負担感が軽減され、互いに意見をやり取りする様子が多く見られた。
中学部10「自分の思いや気持ちを言葉で伝えることが困難で、朝の心的状態が不安定であることが多い生徒に対し、タブレット端末の「Google Forms」や「Google Classroom」を活用して、自分の生活習慣や心的状態を振り返る活動を毎朝行った事例」
概要
・自分の思いや気持ちを言葉で伝えることが困難で、朝の心的状態が不安定であることが多い生徒に対し、タブレット端末の「Google Forms」や「Google Classroom」を活用して、自分の生活習慣や心的状態を振り返る活動を毎朝行った事例である。自分の心的状態を伝える負担感が軽減され、日常の楽しみを見通すことにより、心理的な安定を保ち、自ら他者と関わるようになってきた。
中学部11「平仮名の読みが苦手な生徒の実態に即したアプローチを通して、平仮名の読みがスムーズにできること、さらに平仮名を学習等で活用することができるように取り組んだ事例」
概要
・平仮名の読みが苦手な生徒の実態を、ICT 等の活用によって明らかにし、把握した実態に即したアプローチを通して、平仮名の読みがスムーズにできること、さらに平仮名を学習等で活用することができるように取り組んだ事例である。