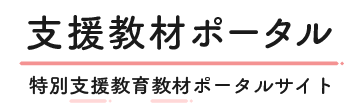実践事例
情報端末機器に慣れ、より主体的に学習に取り組むための指導(継続)
概要
・自立活動を主とした教育課程を履修しており、身体的・心理的なストレスを抱えると体調を崩しがちである。緊張が高まると震えたり表情が固まったりする。
・他者の意図を汲むことや文字(漢字)を読むことなどに困難が見られる。
・タブレット端末やパソコンを扱うことに興味関心度が高いが、操作性は未熟である。
・他者とのコミュニケーションを取ることに時間を要する。(慣れるまでに時間や期間がかかる。)
・初めての場所や集団参加が苦手であり、過度な緊張が見られる。
・他者の意図を汲むことや文字(漢字)を読むことなどに困難が見られる。
・タブレット端末やパソコンを扱うことに興味関心度が高いが、操作性は未熟である。
・他者とのコミュニケーションを取ることに時間を要する。(慣れるまでに時間や期間がかかる。)
・初めての場所や集団参加が苦手であり、過度な緊張が見られる。
月の満ち欠けを確認するための指導
概要
・月がどのように満ち欠けをしているのかを理解できていない。
・体験させたい内容が学校にいる時間中に実施することができない。
・明るい時間帯に観測ができる月だけでは満ち欠けに関連付けることが難しい。
・体験させたい内容が学校にいる時間中に実施することができない。
・明るい時間帯に観測ができる月だけでは満ち欠けに関連付けることが難しい。
製品製作の進捗状況を記録・確認しながら、主体的に作業を進めるための指導
概要
・3人で作業工程を分担しているが、進捗状況を把握しながら作業を進めることが難しい。
・スケジュールを確認しながら、作業を進めることが難しい。
・布の組み合わせに迷い、そのことで時間がかかることがある。
・スケジュールを確認しながら、作業を進めることが難しい。
・布の組み合わせに迷い、そのことで時間がかかることがある。
自作教材(スイッチ)を活用した意思の伝達に関する指導
概要
視覚障害のある重度重複障害児童生徒が、保有する聴覚、触覚等の感覚を十分に活用することにより、感覚の機能が向上するとともに、自己の身体機能に応じて、授業や朝の会に主体的に取り組む意欲を高めることができた。
手指の操作的な活動が難しい場合でも、足や口、頭等他の部位で操作ができるスイッチもいろいろと紹介されている。それらと組み合わせることで、活用の範囲が拡がると考えられる。
また、普段から視覚的な情報を積極的に取り入れて活動している児童たちも、文字情報読み上げソフトウェアを活用した教材や電子絵本には大変興味をもち、一層集中して取り組むことができた
手指の操作的な活動が難しい場合でも、足や口、頭等他の部位で操作ができるスイッチもいろいろと紹介されている。それらと組み合わせることで、活用の範囲が拡がると考えられる。
また、普段から視覚的な情報を積極的に取り入れて活動している児童たちも、文字情報読み上げソフトウェアを活用した教材や電子絵本には大変興味をもち、一層集中して取り組むことができた
視覚障害者用ソフトウェアを活用した視覚障害のある生徒への情報入力支援
概要
点字資料のみを使った調べ学習は効率がよいとは言えない。しかし、インターネット利用の操作方法を十分に習得し、検索キーワードの選択技能も高まると、目的のサイトに早く到達できるようになった。頻繁にアクセスするサイトについては、だいたいの画面構成がイメージできるため、必要な内容を適切に切り取り、保存できるようになった。自力で素早く調べものができる喜びは本当に大きなものである。
コンピュータを活用した視覚障害のある生徒への社会自立支援
概要
情報を自力で作成し送受信するスキルを身に付けることは、視覚障害児の児童生徒にとってコミュニケーションおよび職域の広がりに直結する。ワープロ検定受験を目標に正確なキータッチを心がけた結果、4級の検定資格を得ることができた。文字入力速度は10分で300字程度と確実に向上しているため、3級の取得とともに表計算ソフトウェアの操作技術の習得を希望している。表計算ソフトウェアについても、ショートカットキーの活用や、視覚障害者ソフトウェアの導入によって、全盲
の児童生徒にも操作できるため、資格取得をクラス生徒全員が希望するよい動機付けとなった。
の児童生徒にも操作できるため、資格取得をクラス生徒全員が希望するよい動機付けとなった。
ゲームを活用したコンピュータ等に慣れ親しむ活動の充実
概要
ソフトウェア(ゲーム)や教師の支援が内容が児童の実態に合っていたため、3名の児童は全員、マウスやソフトウェアの役割や使い方を理解し、上手に操作することができるようになった。
プレゼンテーションソフトウェアを活用した自閉症等のある児童生徒への視覚的な支援
概要
全校集会などでこのような視覚的支援の活用を進める中で、児童生徒も徐々に慣れてきて、スクリーンをよく見るようになって
きた。卒業式では、スクリーンをステージ中央に配置することにより、話す人とスクリーンが視野に収まり、顔(視線)を動かさなくても見えるので、意識を集中することができた。
また、児童生徒の実態に合わせた教師の言葉かけにより、多くの児童生徒が見通しをもって参加できるようになり、「あと3つで終わり」、「次は、○○」などと教師に話しかける児童生徒も現れてきた。卒業式後のアンケートにも「式の流れや見通しがもてるようになってよかった」「是非、続けていくべきである」などの意見が多く寄せられた。
これらの支援をきっかけに、普段の授業でも予定や流れを黒板や紙に書いて最初に生徒へ知らせたり、小さなカード等を利用したそのほかの簡単な視覚的支援をしたりするなど、ちょっとした支援や配慮により効果が現れる場面が増えてきたように思われる。
きた。卒業式では、スクリーンをステージ中央に配置することにより、話す人とスクリーンが視野に収まり、顔(視線)を動かさなくても見えるので、意識を集中することができた。
また、児童生徒の実態に合わせた教師の言葉かけにより、多くの児童生徒が見通しをもって参加できるようになり、「あと3つで終わり」、「次は、○○」などと教師に話しかける児童生徒も現れてきた。卒業式後のアンケートにも「式の流れや見通しがもてるようになってよかった」「是非、続けていくべきである」などの意見が多く寄せられた。
これらの支援をきっかけに、普段の授業でも予定や流れを黒板や紙に書いて最初に生徒へ知らせたり、小さなカード等を利用したそのほかの簡単な視覚的支援をしたりするなど、ちょっとした支援や配慮により効果が現れる場面が増えてきたように思われる。
携帯ゲーム機・無線LANを活用した学校行事等における視覚的な支援
概要
○ 通常の要約筆記で行うスクリーンを使う方法に比べ、児童生徒は立ち位置を選ぶ必要がなく、行動範囲の制約がない。
○ 手元に情報が表示されるので、資料等を活用するときには視線を変えずに行うことができる。
○ 「手話」に比べ、一度に得ることができる情報量が多いので、児童生徒に考える時間を提供することができる。
○ 手元に情報が表示されるので、資料等を活用するときには視線を変えずに行うことができる。
○ 「手話」に比べ、一度に得ることができる情報量が多いので、児童生徒に考える時間を提供することができる。