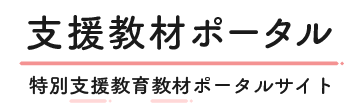実践事例
紙を破く不適切行動を別の行動へ変えるための指導
概要
・絵本や絵本をコピーした紙を切り取り、コレクションすることが好きだが、コレクションする手順に失敗した紙や飽きた紙を、破くことで終わりにする。破いた後に同じものが欲しいと要求することがある。
・紙や布の少しのほつれが気になると、全て破くまで気が済まない。
・紙や布の少しのほつれが気になると、全て破くまで気が済まない。
全体で発表するための支援
概要
・伝えたいことや、発表したいことがあっても、自分の言葉で話すことに抵抗がある。
・周りの人が笑顔になったり、盛り上がったりすることに関心が強いが、そのための手段が少なかった。
・iPadのアプリ「えにっき」「ごじゅーおん」等を使えば、人前で発表することができていた。
・周りの人が笑顔になったり、盛り上がったりすることに関心が強いが、そのための手段が少なかった。
・iPadのアプリ「えにっき」「ごじゅーおん」等を使えば、人前で発表することができていた。
朝の会の天気係で、今日の天気をお知らせするための指導
概要
・人工呼吸器、経鼻経管栄養、吸引(必要に応じて、常時メラチューブ挿入)
・眼球、口唇の左端、右手親指、左手中指の各部位をわずかに動かすことができる
・話しかけに対して、動かせる部位を動かして応えようとする
・眼球、口唇の左端、右手親指、左手中指の各部位をわずかに動かすことができる
・話しかけに対して、動かせる部位を動かして応えようとする
「予定表をアプリを活用して作成し、操作しながら係活動に取り組むための指導」
概要
・言語によるコミュニケーションはできる。
・学習課題に対しては、積極的に取り組む。
・情報機器の操作は、基本的操作方法を伝えると、一人でできる。
・学習課題に対しては、積極的に取り組む。
・情報機器の操作は、基本的操作方法を伝えると、一人でできる。
ものを見る力を鍛えるための指導
概要
・注意が転導しやすく、手元を見ずに作業をすることがある。
・ものをよく見て選ぶことや、空間認知、色や形を把握することが難しい。
・興味のある活動でないと、集中が続かないことが多い。
・ものをよく見て選ぶことや、空間認知、色や形を把握することが難しい。
・興味のある活動でないと、集中が続かないことが多い。
自分や友だちの描いた作品を鑑賞するための指導・支援
概要
①一つの活動に対して、集中を持続することが難しい
②提示されたものを見るとき、視線は向けるが、見続けることは難しい
③興味があるものに関しては、見続けることもある
②提示されたものを見るとき、視線は向けるが、見続けることは難しい
③興味があるものに関しては、見続けることもある
平仮名の文字とものの対応を学ぶための指導
概要
・特定の言葉を話すことができるが、音声表出できる語彙数が少ない。
・平仮名の文字と音声が一致しない。
・文字(単語)と物(イラストや写真)の対応が困難。
・エラーをしたり、難しいと感じたりする課題には抵抗感を示したり癇癪を起こしたりする。
・平仮名の文字と音声が一致しない。
・文字(単語)と物(イラストや写真)の対応が困難。
・エラーをしたり、難しいと感じたりする課題には抵抗感を示したり癇癪を起こしたりする。
他者との関わりや自分の役割を感じられる合同授業の工夫 ~重度重複障がい児の教科学習の充実に繋がるICT活用~
概要
・知的、肢体不自由等の障がいを併せ持つ。
・医療的ケアが必要な生徒も複数名在籍する。
・日常生活面では全介助を要する。
・発語がない生徒が多く、意思の表出は表情の変化や簡単な手指操作に限定される。
・医療的ケアが必要な生徒も複数名在籍する。
・日常生活面では全介助を要する。
・発語がない生徒が多く、意思の表出は表情の変化や簡単な手指操作に限定される。
身体の動きを活かして音楽的活動をする指導・支援
概要
・病院に長期入院しており、登校日は限られている。(主にベッドサイド授業)
・病室に一般の入院患者もいることから、本物の楽器を演奏することが難しい
・発語はなく、また瞳に軟膏を塗る処置を必要とするため、聴覚・触覚へ訴えかけるような題材がよい
・障がいの状況や常時必要なケアにより、身体の可動域が限られている
・病室に一般の入院患者もいることから、本物の楽器を演奏することが難しい
・発語はなく、また瞳に軟膏を塗る処置を必要とするため、聴覚・触覚へ訴えかけるような題材がよい
・障がいの状況や常時必要なケアにより、身体の可動域が限られている
自分で伝えたり発表したりするための支援
概要
・言葉でコミュニケーションを図ることが難しく、発表の場では教師が自分の代わりに発表してくれるのを待つ傾向にある。
・選択をする場面では、指さしか頷きなどで意思表示をしている。
・短い文章で済む自分がどうしても伝えたいことは、筆談で教員に伝えることができる。
・客観的に自分のことを捉えることが難しく、現場実習等でコミュニケーションの課題を度々指摘されているが、本人はそのことを課題や困りとして捉えられていない。
・選択をする場面では、指さしか頷きなどで意思表示をしている。
・短い文章で済む自分がどうしても伝えたいことは、筆談で教員に伝えることができる。
・客観的に自分のことを捉えることが難しく、現場実習等でコミュニケーションの課題を度々指摘されているが、本人はそのことを課題や困りとして捉えられていない。