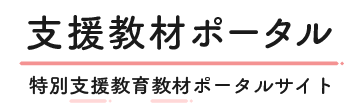実践事例
音声を入れてお話づくりをしよう
概要
状況に応じた言葉で表現し、自分の考えを伝えることができる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
端末に自分の声を録音することで、聞き返すことができ、自分が相手に伝わる話し方ができているか、語尾や声のトーン、スピードなど、伝え方で印象が変わるということを体感させることをねらいとした。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
端末に自分の声を録音することで、聞き返すことができ、自分が相手に伝わる話し方ができているか、語尾や声のトーン、スピードなど、伝え方で印象が変わるということを体感させることをねらいとした。
テーマを決めて写真を撮ろう!
概要
・ルーブリックに沿って、テーマに合う写真を撮ることができる。
・ペアと協力することを通して、コミュニケーション力を養う。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・テーマに合う写真を撮ることで、色・形などを認識する力を高める。
・写真をスライドに貼ることで、テーマに合った写真になっているか再確認する。
・ペアで写真を撮り、取捨選択したり、それを Google スライドに貼ったりするなどの活動を通して、情報活用能力やコミュニケーション力を高める。
・ペアと協力することを通して、コミュニケーション力を養う。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・テーマに合う写真を撮ることで、色・形などを認識する力を高める。
・写真をスライドに貼ることで、テーマに合った写真になっているか再確認する。
・ペアで写真を撮り、取捨選択したり、それを Google スライドに貼ったりするなどの活動を通して、情報活用能力やコミュニケーション力を高める。
プログラミングでニミカーを動かしてゴールをめざそう
概要
・粘り強く課題に取り組み、プログラミング的思考を養う
・問題解決のために他者と協力して課題に取り組むことで、その喜びや必要性を実感し、コミュニケーション能力の向上の素地を培う。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・ロイロノートの web カードを使って課題の配付やプログラミングソフトへのアクセスを容易にすることで、活動時間を多く確保できるようにした。
・共有ノートを活用することで子ども同士の交流を活発化することをねらいとした。
・実際に、自分で考えたことをプログラミングで動かすことで、成功した実感をもたせるとともに、うまく動かなかったときに、試行錯誤しながら間違えた理由を主体的に考えられるようになることをねらいとした。
・問題解決のために他者と協力して課題に取り組むことで、その喜びや必要性を実感し、コミュニケーション能力の向上の素地を培う。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・ロイロノートの web カードを使って課題の配付やプログラミングソフトへのアクセスを容易にすることで、活動時間を多く確保できるようにした。
・共有ノートを活用することで子ども同士の交流を活発化することをねらいとした。
・実際に、自分で考えたことをプログラミングで動かすことで、成功した実感をもたせるとともに、うまく動かなかったときに、試行錯誤しながら間違えた理由を主体的に考えられるようになることをねらいとした。
1学期の活動をふり返ろう
概要
支援学級での1学期の学習や活動を振り返ることができる。
文章作成アプリケーションを使って支援学級通信「カラフル」を、「伝える相手」のことを考えながら作成することができる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
iPad にインストールされている Apple のネイティブアプリケーションである文章作成ソフト(Pages)を活用することで、文章だけでなく画像を挿入した支援学級通信を作成できることをねらった。
デジタルコンテンツを使用して支援学級通信を作成することで、文字を書くことが苦手な児童やレイアウトが苦手な児童や発表が苦手な児童が、苦手意識を減らして積極的に活動に参加できることをねらった。
支援学級の保護者に情報発信する過程で、自分たちの経験を言語化し、感じたことや楽しかったことなどを全員で交流し共有する。交流を通して「どうしたら相手に分かりやすく伝えられるか」を考えることをねらった。
文章作成アプリケーションを使って支援学級通信「カラフル」を、「伝える相手」のことを考えながら作成することができる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
iPad にインストールされている Apple のネイティブアプリケーションである文章作成ソフト(Pages)を活用することで、文章だけでなく画像を挿入した支援学級通信を作成できることをねらった。
デジタルコンテンツを使用して支援学級通信を作成することで、文字を書くことが苦手な児童やレイアウトが苦手な児童や発表が苦手な児童が、苦手意識を減らして積極的に活動に参加できることをねらった。
支援学級の保護者に情報発信する過程で、自分たちの経験を言語化し、感じたことや楽しかったことなどを全員で交流し共有する。交流を通して「どうしたら相手に分かりやすく伝えられるか」を考えることをねらった。
もっと、みんなと話したい!
概要
友だちともっと会話が続けられるよう、自分の姿をふりかえり、動画や文字起こしされた文章を参考にしながら、会話の仕方を考えることができる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・友だちともっと楽しく話したいという思いに応え、撮影した動画や文字起こしされた文章から自分の姿をふりかえることができる。
・動画やアプリで記録することで、自分の会話をふりかえることができるようにする。
・NHK for school の動画を視聴し、会話の広げ方の例を見ることで、自分が会話する際の参考にできるようにする。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・友だちともっと楽しく話したいという思いに応え、撮影した動画や文字起こしされた文章から自分の姿をふりかえることができる。
・動画やアプリで記録することで、自分の会話をふりかえることができるようにする。
・NHK for school の動画を視聴し、会話の広げ方の例を見ることで、自分が会話する際の参考にできるようにする。
よりよい言い方を考えよう
概要
立場の違いによって様々な感じ方があることを知り、よりよい言い方をした時の気持ちについて考える。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・ロイロノート内の提出箱に撮影した動画を提出する。その動画を確認しながら、考えやわかったことをかけるようにする。
・動画の気になるところを巻き戻したり、何度も見たりすることで自分の考えを書く時のヒントにできるようにする。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・ロイロノート内の提出箱に撮影した動画を提出する。その動画を確認しながら、考えやわかったことをかけるようにする。
・動画の気になるところを巻き戻したり、何度も見たりすることで自分の考えを書く時のヒントにできるようにする。
打ち上げ花火の絵をかこう
概要
・色や形づくりを楽しむ。
・友だちの作品の鑑賞を通じ、自分の意見を発表する。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
花火という言葉だけではイメージしにくい児童にとって、動画等の視覚支援を行うことで集中してみることができ、イメージしやすい。
Chromebook の描画キャンパスを使うことで、手を汚すことやクレヨンのにおい等を気にせず作品を制作することができ、すぐに消すことができるので、何度でも挑戦できる。
・友だちの作品の鑑賞を通じ、自分の意見を発表する。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
花火という言葉だけではイメージしにくい児童にとって、動画等の視覚支援を行うことで集中してみることができ、イメージしやすい。
Chromebook の描画キャンパスを使うことで、手を汚すことやクレヨンのにおい等を気にせず作品を制作することができ、すぐに消すことができるので、何度でも挑戦できる。
12 月の掲示物を作ろう
概要
○オクリンクに送られた進め方カードをもとに、12 月の掲示物を作成することができる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
○12 月の掲示を大型提示装置に写し、作り方の説明を聞くことで共通理解を図ることができる。
○それぞれのタブレットに送った進め方のカードを見ながら、順番に従って、掲示物を作ることができる。
○出来上がった自分の作品を大型提示装置に写し、発表することができる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
○12 月の掲示を大型提示装置に写し、作り方の説明を聞くことで共通理解を図ることができる。
○それぞれのタブレットに送った進め方のカードを見ながら、順番に従って、掲示物を作ることができる。
○出来上がった自分の作品を大型提示装置に写し、発表することができる。
さいほう名人になろう
概要
・針に糸を通したり、糸を結んだりなどの微細運動を通して、指先の感覚を鍛える。
・本返し縫いを使って、自分の作品をつくる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・玉結びや玉止め、本返し縫いの方法などを、ロイロノート・スクールのヒント動画を見て、前時までの学習を思い出しながら自分のペースで活動できる。
・動画を視聴することで、もう一度見たい場所や一時停止したい場所を選ぶことができ、自分でヒントを選択する練習になる。
・本返し縫いを使って、自分の作品をつくる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・玉結びや玉止め、本返し縫いの方法などを、ロイロノート・スクールのヒント動画を見て、前時までの学習を思い出しながら自分のペースで活動できる。
・動画を視聴することで、もう一度見たい場所や一時停止したい場所を選ぶことができ、自分でヒントを選択する練習になる。
助けてレスキューに挑戦!
概要
安心する言葉をかけるタイミングを知り、ペアの状況に合わせて適した言葉がけをすることができる。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・タブレットを使うことにより、動画の中からめあての場面を切り出すことが容易であることや、切り出した場面にセリフを貼り付けるなどの作業も容易である
ことから、活動の時間を確保できる。
・別のチームの考えを共有する際に場面を写真で確認できるため、言葉や文章よりもイメージしやすく、自分事として向き合いやすくなることをめざす。
本時における 1 人 1 台端末の活用方法とそのねらい
・タブレットを使うことにより、動画の中からめあての場面を切り出すことが容易であることや、切り出した場面にセリフを貼り付けるなどの作業も容易である
ことから、活動の時間を確保できる。
・別のチームの考えを共有する際に場面を写真で確認できるため、言葉や文章よりもイメージしやすく、自分事として向き合いやすくなることをめざす。